静岡大学教職員組合主催の学内教職員研究集会が 2019年12月5日(木) に開催されました。静岡大学の統合再編問題と大学のガバナンスについて考えました。
田島慶吾人文社会科学部副学部長が「静岡大学の統合再編問題と「大学のガバナンス」-大学自治は死んだのか」という題で講演しました。
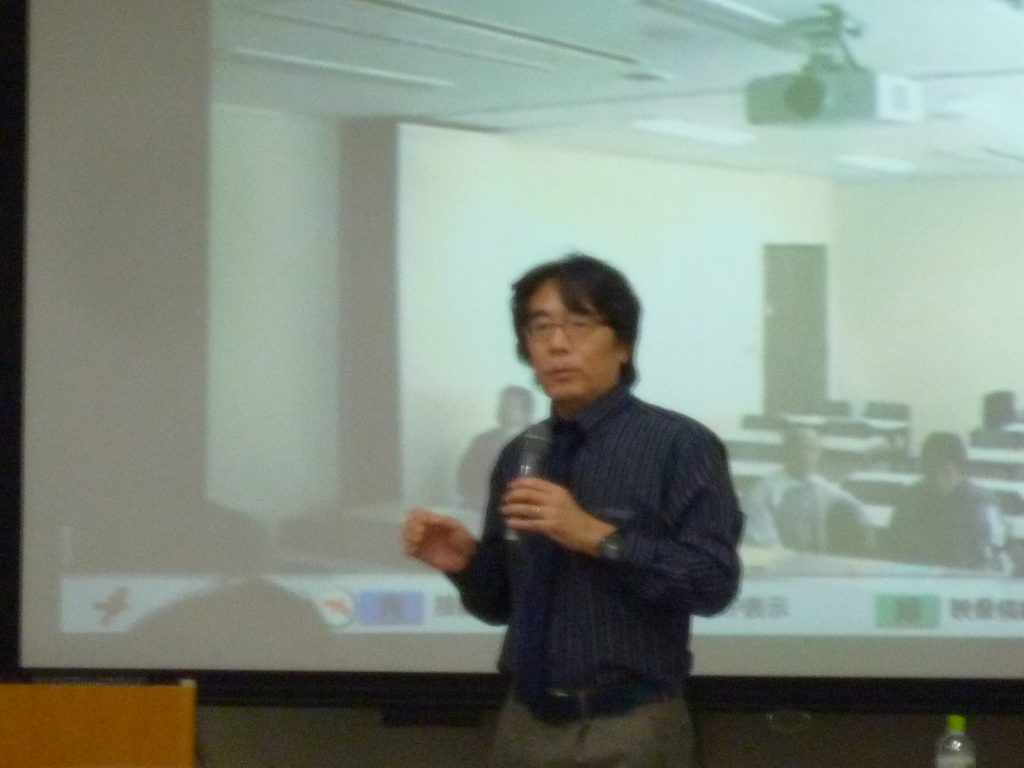
「大学のガバナンス」の定義が明確になされた公文書が存在しないことを示したうえで、「大学のガバナンス」を取り上げている文書からその定義化を試み、「コーポレート・ガバナンス」や海外の「大学のガバナンス」の定義との比較を行いました(田島先生の専門は経済学です)。
その結果、日本の「大学のガバナンス」には、「組織の長(理事長・学長)の行動の監視」が欠落しており、学長による専横を抑制できないという潜在的な欠陥があることが明らかになりました。また、この欠陥がすでに現実問題となっていることを、静岡大学の統合再編問題を挙げて示しました。
次に、川瀬憲子人文社会科学部教授が「地域から考える大学再編」という題で講演しました。
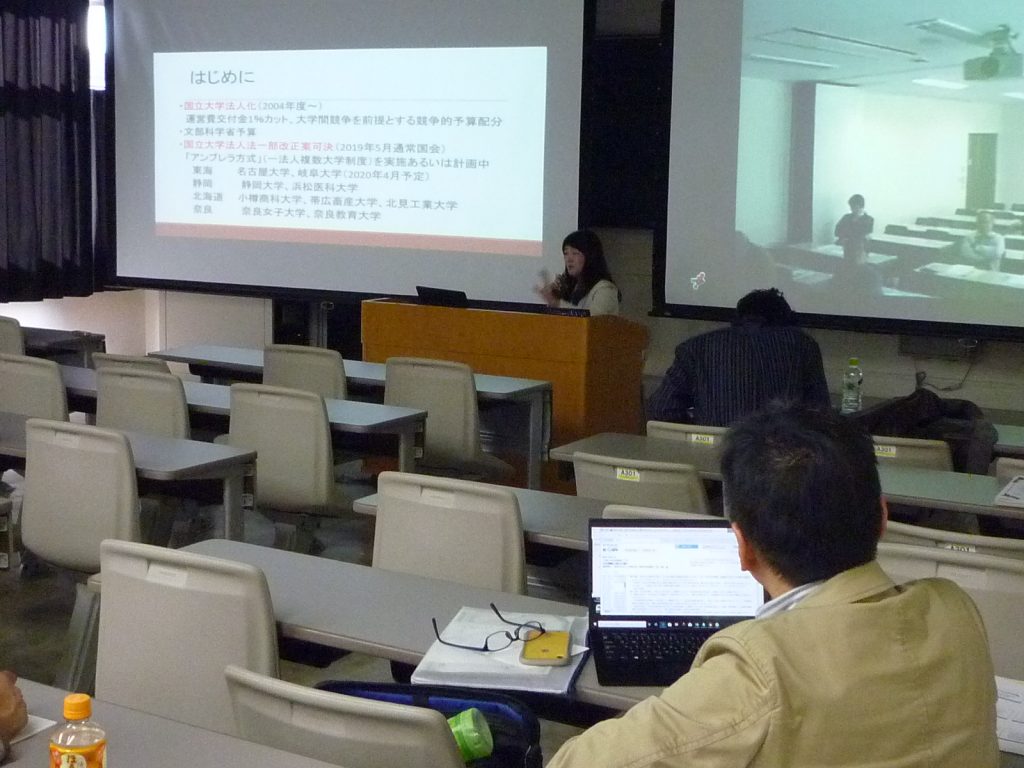
静岡大学の統合再編問題がどのように自治体と関わっていたのかについて解説があり、静岡市と浜松市でその関わり方に大きな違いがあったことが紹介されました。 また、アンブレラ方式による大学統合の例として、名古屋大学―岐阜大学、大阪市立大学―大阪府立大学が紹介されました。
それらの先行大学では、高等教育が有するサービスとしての性質や公共財としての学術研究の意義の観点から、経営の効率化が大学再編のモチベーションになっていることに対する疑問の声があがっているそうです。また、自治体の統合再編を例に挙げ、統合には「コスト」がかかるとの指摘がありました。
会場からは、
「統合に向けて事務が煩雑になることへの懸念が先行大学の職員の中から上がっており、 統合に分割を伴う静大の場合は相当の覚悟が必要だし、法人事務局の静大への設置が予想されることから、 浜松医科大の職員は人員削減が心配だろう。」
「入試問題の作成や教養授業はどうなるのか?」
などの声がありました。
川瀬先生の講演資料はこちらです。
「地域から考える大学再編」
掲載写真は静岡大学教職員組合事務局から提供いただきました。